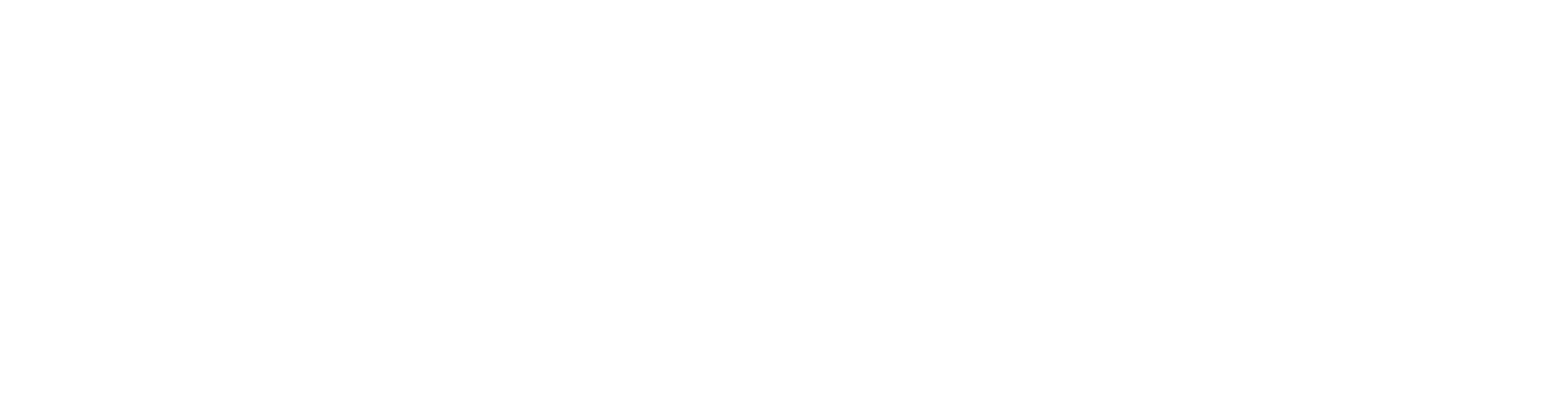7月30日に発生したカムチャッカ地震に起因する津波に関する当社の見解
カムチャッカ地震に関連し、気象庁は即座に 「津波警報 (1- 3m)」 及び 「津波注意報 (0.2-1m)」を発令しました。
7/30 8:25 日本全国に発令(北海道・東北・関東・東海向けは警報、西日本は注意報)
18:30 関東・東海向けの警報を注意報に切り替え
20:45 北海道・東北向けの警報を注意報に切り替え
7/31 10:45 西日本向けの注意報が解除
16:30 他の地域向けの注意報も解除
<能登地震の際に発令された「大津波警報 (3m以上)」は、今回は発令されず。>
警報が与えた市民生活への影響はかなり大きいものでした。
警報・注意報発令中には、三重県の58歳の女性が避難中に自動車で崖下に転落して亡くなられた他、避難中に体調を崩して病院に搬送された人は相当数に及びました。
東海道本線(東京-熱海間)は、警報発令とほぼ同時(8:28)に運行を見合わせ、同日21:00から順次運行を再開するまで完全運休。仙台空港は閉鎖されて56便が欠航。海上の定期便は52便が運休。避難のための交通量が増えて交通渋滞は多発。 一部高速道路の閉鎖もあり。総じて経済的損失は相当額に及ぶと思われます。
実際には、幸にして、日本海岸を実際に襲った津波の規模は小規模でした。
観測された最大波高は、岩手県久慈港で1.3 m(7/31 13:52)。仙台港の 0.9 m(7/31 23:20)、八戸港の0.8 m(7/31 18:15)がこれに続きます。(いずれも、第一波ではなく、海底山脈または島しょに反射して発生した後続波等が重なり合った波でした。)しかし、関東、東海、その他の地域では、最大でも0.5m程度でした。
「今回の警報の発令はやや過剰だったのではないか」という批判もあるようですが、津波は、海岸や海底の地形によって様々に変化するものであり、場合によっては予想外の増幅をもたらすこともあるので、その批判は酷でしょう。避難勧告には「十分な安全率を見ること」はいずれにせよ必要です。
しかし、実際の津波の状況を、よりきめ細かく観測する方法は現実に存在するのですから、そのような方策を深く研究して、少しでも「警報を過剰なものにしない」ための努力をすべきは当然だと思います。
もし気象庁に、「十分安全率を見た警報は出した。あとは住民(または地方自治体)の責任」という考えがあるとすれば、それは問題かもしれません。2024年に発表された関西大学の高橋教授(現学長)と奥村教授の論文にもある通り、「警報だけで避難する住民は実際に避難が必要な住民の20%にも満たず、あとの人達は、周囲がざわざわしてきて初めて避難を考える」とされています。ということは、「警報を出すだけでは不十分で、岸に近づいてくる津波の実態を、できるだけ継続的にきめ細かく知らせ続ける」誠意がなければ、人の命は救えないということを意味します。
また、「警報を出して、かなり時間が経ってからそれが解除された。その間実際には殆ど何も起こらなかった」ということが続けば、多くの人々に「次第に警報を軽視する癖がついてしまう」というリスクが生まれることも危惧されます(オオカミ少年現象)。
今回のカムチャッカ津波に関係して、当社の立場からみた見解を申し上げるとすれば、下記のようになるかと思います。
- 今回の津波は現実には極めて軽微なものだったので、当社が静岡県沿岸に設置していた海洋レーダー施設では、有意な検知はほとんどなされませんでした。
- 7/30 21:50に気象庁が御前崎に設置した潮位計は、今回のこの地域での最大
級である40 cmの津波を計測していますが、この津波は、志摩半島の南方約100 km(東経33.5度 北緯 137度 水深約2,000 m)の海底に設置されたDONETの計測器では、同日 11 : 30ごろに約 2 cmの津波が襲来したことが計測されています。(DONETの観測点の東端はこの地点で、静岡県の真南には観測点がありません。)
- 一般論としては、この程度の小さい津波は、当社の海洋レーダーが把握する極めて小さい流速変化は、雑音に影響されて埋没してしまい、有意な変化として計測することはできません。しかし、今回も、ノイズの小さい時間帯(7月31日03時から06頃)において、海岸より12 kmの水深50m未満の浅海の海域では、当社のレーダによっても、30㎝程度の津波を検知できました。
- 仮に今回の津波がもっと大きなものであったなら、当社の海洋レーダー施設は、津波がDONET、S-net、N-netなどの観測点で計測された後も、それを越えて海岸に向かう間、広い海面での計測を継続し続け、時々刻々と状況を伝えることができたと思われます。
- 上記は、DONET、S-net、N-net のような巨額の費用をかけて建設したシステムが存在している場所でも、ORNISのシステムはそれなりの重要な役割を果たせることを語っておりますが、このようなシステムが存在していない場所(例えばS-netとDONETのカバー範囲の隙間)、更にはこういったシステムの建設が将来とも財務的に困難と思われる場所(例えば日本海沿岸)では、その貢献は格段に大きいものになるでしょう。
- 更に言うなら、沖に流された人達の救出や救援物資の早期搬入のためには、津波が引いて行った後の海面の状況を正確に知る必要がありますが、これについてもORNISのシステムは多大な貢献ができますし、それ以外には現状ではいかなるシステムもこの役割を果たせません。
以上を総合し、当社としては、気象庁には「当社のシステムの有益性と信頼性」及び「コストの妥当性」を十分に検証していただき、「住民に対して警報や注意報を出すことが義務付けられている唯一の政府機関」として、その責務の履行に万全を期していただけるよう、切にお願いしたい次第です。